【補助】障がいのある方への手当
特別障害者手当
精神または身体に重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護が必要な方に対して、手当を支給することにより、福祉の増進を図るものです。
支給要件
20歳以上で、日常生活で常時特別の介護が必要であり、障害年金の1級程度の障害が重複しているなど、著しく重度障害の状態にある方が対象です。支給を受けるためには次の条件にも該当しなければなりません。
- 受給者・配偶者・扶養義務者の所得が一定の額以下であること。
- 施設に入所していないこと。
なお、特別障害者手当受給中に3か月以上入院した場合は、受給資格を失います。
手当の額
月額 29,590円/月(令和7年度~)
支払い月 年4回(5月・8月・11月・2月)
認定請求に必要なもの
1.特別障害者手当認定請求書(福祉課、各支所地域生活課にあります。)
2.所定の診断書(福祉課、各支所地域生活課にあります。)
3.公的年金証書
4.身体障害者手帳または療育手帳(お持ちの方のみ)
5.通帳(請求者様ご本人名義のもの)
6.印鑑(認印可)
7.個人番号が確認できるもの及び身元が確認できるもの。
手当を受けている方の必要な届け出
●所得状況届
・受給者全員が毎年8月12日から9月11日までの間に提出します。
・2年間提出しないと受給資格がなくなることがあります。
●障害状況届
・有期認定になっている方は、定められた期間に認定診断書等を提出して、引き続き手当が受けられるか再認定を受けなければなりません。
●額改定届
・障害の程度が変わったとき。
●資格喪失届
・受給者が施設(老健施設は除く。)に入所したとき。
・受給者が3か月以上医療機関又は老健施設に入所となったとき。
・受給者が死亡したとき。
・受給者が日本国内に住所がなくなったとき。
・受給者の障害程度が、本制度の定める障害程度に該当しないほど軽減したとき。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6428
ファックス番号:0894-62-3055
メールフォームによるお問い合わせ
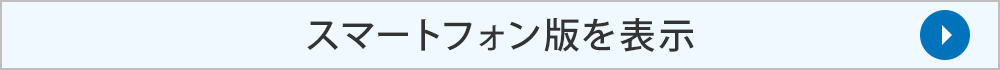





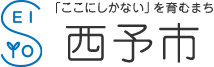

 検索
検索 翻訳
翻訳 メニュー
メニュー
更新日:2023年12月09日