【報告】【5年生 第1回目】プロジェクト始動!復興を考える学習(令和4年4月27日)
プロジェクト始動!
始動した「復興水辺域プロジェクト」。
最初の授業の講師は、愛媛大学社会共創学部の松村暢彦教授。「西日本豪雨からの野村の復興まちづくり」と題し、災害以後どのような形で復興が進められてきたのかを学びました。

▲ 学習風景

▲ 講師の松村教授
野村では、地域住民、企業、大学など多くの人々が関わりながら野村の将来を考えています。その中心となっている「のむら復興まちづくりデザインワークショップ」の活動内容などを紹介しました。
その中で出たアイディアや意見をもとにまちの将来像が出来上がったことを知ると、児童たちからは「早く出来上がってほしい」「ここで友達と遊びたい!」「楽しみ」といった声が挙がりました。
また、「復興」の「興」という字は、「上下2つの筒」と「4つの手で物をあげる」象形から、力を合わせて物をあげることを表現していることを知り、復興に向けて色々な人々が力を合わせることが大切だということを学びました。

▲ 模型でまちの将来を学ぶ

▲ 児童の学習メモ
どんな活動がしたい?みんなでワークショップ
野村の復興を学んだあとは、河川沿いの将来像(基本設計の図面)をもとに、自分たちがしてみたい活動を皆で話し合いました。
様々なアイディアが出る中で、最終的に3つのテーマに絞りました。
○さつまいもの栽培
○ひまわりの育成
○肱川の生物調査
令和3年度から野村高校生が取り組んでいる菜園共創プロジェクト(被災した農地を活用してさつまいもやひまわりを育て地域活性化につなげていく活動)を見ていた児童や先生たちから、自分たちもやってみたいという意見が多く出たことや、近くにありながらあまり遊んだりしたことのない肱川をもっと知りたいという意見から、上記3つの活動を行っていくことを決めました。


後日、この3つのテーマをもとに年間計画をつくりました。
今後この計画に沿って、地域の方々や大学などの協力をいただきながら活動を進めていきます。

▲ 年間計画
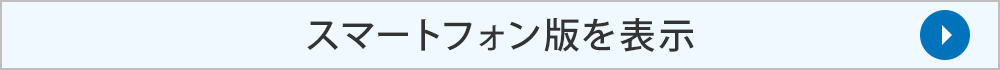





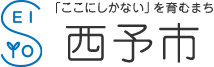

 検索
検索 翻訳
翻訳 メニュー
メニュー
更新日:2022年04月27日